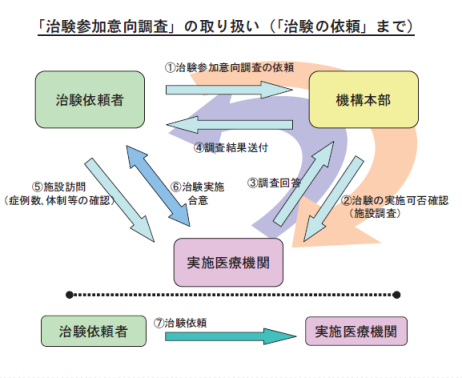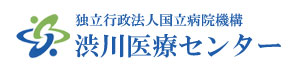
臨床研究部
臨床研究は、医療の質をより向上させるためになくてはならないものです。臨床研究とは、疾患の診断・治療・予防などの方法を改善するために「人」を対象にして行う研究のことをいいます。国立病院機構では、診療、教育、臨床研究を3大事業としており、現在、国立病院機構において、臨床研究センター10施設、臨床研究部75施設が設置されております。当院は国立病院機構に設置された臨床研究部75施設のうちの一施設として、積極的に国内外の治験や、多施設共同臨床研究を重視し、EBM推進研究、国立病院機構はじめとする多くの施設との共同研究に参加、また多数の学会、および論文発表を行っています。
当院の特色として、血液関連疾患(リンパ腫や多発性骨髄腫など)、肺癌や消化器癌などの固形癌、重症心身障害、感染症では国内でも有数の治験・臨床研究実績があります。また、厚生労働省からの研究依頼、群馬の地域病院が連携して行う研究にも積極的に参加しています。
臨床研究部長のあいさつ

2025年4月に臨床研究部長として就任いたしました。私は、2003年に群馬大学卒業後、群馬大学第3内科(現在、血液内科)に入局し、2007年、群馬大学大学院に入学した矢先に夫の米国留学に同行することとなりました。当時若かったこともあり、怖いもの知らずで、何の研究経験、実績もないまま「造血幹細胞の研究をさせてください。」とラボを自ら探してピッツバーグ大学の研究室に飛び込んでいったのが研究のスタートでした。帰国後も共同研究員として、慶応義塾大学、発生分化生物学教室で造血幹細胞の研究と、現在にもつながる多発性骨髄腫の研究を行いました。博士取得後は、群馬大学血液内科、および同院輸血部に勤務し、2019年以降、渋川医療センター血液内科で診療、臨床研究、輸血療法に従事してまいりました。
新しい医薬品・医療機器を世界に送り出し、「未来」の患者さまが新たな医療の恩恵を受けるためには、治験(国内で新しい医薬品や医療機器の使用許可を得るために行われる臨床試験)をはじめ、臨床研究が欠かせません。そのためには、患者さまやそのご家族のご理解とご協力がきわめて重要です。当院では、前身の「国立療養所西群馬病院」時代から、「がん」および「感染症」分野における治験や臨床研究は優れており、現在も、毎年多数の治験や臨床研究を行っております。
若輩者ではございますが、当院でこれまで築き上げてきた臨床研究部をさらに発展させていくために、リサーチマインドを育て、次世代につなげていけるよう、日々精進してまいりたいと思います。治験・臨床研究には、患者さま及び地域の先生方のご協力が不可欠です。今後、これまで以上に渋川医療圏・北毛地区地域中核病院として、治験・臨床研究を発展させていくよう、臨床研究部として一丸となって推し進めていきたいと考えておりますので、ご支援ご指導よろしくお願いいたします。
臨床研究部長 入内島 裕乃
治験管理室の紹介
当院の研究部門は、病態研究室、診断法研究室、治療法研究室、治験管理室の4部門に分かれて活動しています。当院の治験管理室では、室長1名(併任)、治験主任1名、主任補佐1名、臨床研究コーディネーター(Clinical Research Coordinator)(院内4名、外部4名)、事務員2名で業務を行っています。CRCは研究遂行に不可欠です。当院では、2025年度から院内CRC 4名に増員し、外部派遣常駐のCRCとともに多くの治験、国内外の共同研究に数多く参加しています。そのような治験・臨床研究がスムーズに行えるようお手伝いするのが治験管理室の役割です。CRCが、治験に参加を考えている患者さまに対して、同意取得の補助、治験参加中の来院スケジュールの確認、調整、相談の対応、来院時のサポートと服薬状況やアンケート類の記入などの確認と補助を行っています。医師に対しては、説明文書・同意文書作成の補助、患者さまの治験適格性のスクリーニング、治験スケジュールの管理、症例報告書の作成補助などを行っています。看護師に対しては、観察項目や検体採取に関する事柄、治験薬投与当日の一連の流れなどについて説明を行い、薬剤師に対しては治験薬払い出しや注射剤などの調製方法に関しての具体的な手順の説明と治験薬の管理について、検査・放射線科に対しては、特殊な検体や検査における取り扱いや手順の説明、相談、確認を行っています。
このように、治験では多職種連携が必須となっており、綿密なコミュニケーションが重要と考え、私が臨床研究部長に着任後、毎月1回、治験管理室会議を開催し、円滑に業務が遂行されるよう努めています。